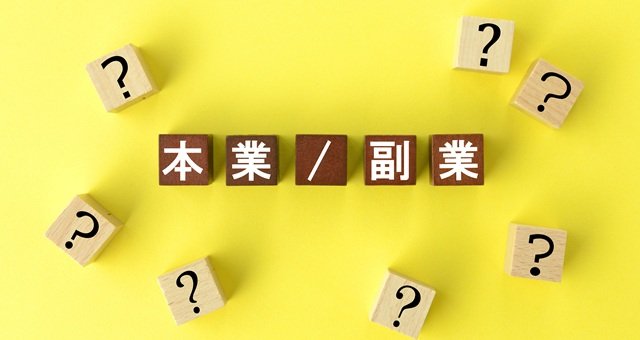ポイント
会社の就業規則では、従業員に対して副業を禁止・制限している会社が多く見られます。一般的な投資は副業に当たらないと思われますが、事業への参画などを伴う場合は副業に当たると判断されるかもしれません。
本記事では、投資は副業に当たるのかどうかなど、会社員の方が投資へ取り組む際に、本業との兼ね合いで注意すべきポイントを解説します。
投資は副業に当たるのか?就業規則による副業制限との関係性
就業規則によって副業が禁止・制限されている場合でも、一般的な投資は副業に当たらず認められると考えられます。
ただし、他の会社の役員に就任する場合や、事業として投資を行う場合などには副業に当たり、本業の勤務先との間でトラブルになるおそれがあるので要注意です。
就業規則における副業規定の具体例
多くの会社の就業規則では、副業・兼業に関する規定が設けられています。就業規則における副業規定の具体例を見てみましょう。
■モデル就業規則における副業規定|原則として副業OK
近年では、勤務時間外の副業は認めるべきという風潮が高まってきました。
その風潮を反映して、厚生労働省が公表しているモデル就業規則では、原則として勤務時間外の副業を認める旨が定められています。
(副業・兼業)
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
モデル就業規則の副業・兼業規定の対象とされているのは、「他の会社等の業務に従事すること」です。
他の会社に雇用されて従業員として行う業務のほか、事業主として行う業務や、請負・委託・準委任契約によって行う業務も対象に含まれます。
■副業・兼業の許可制または禁止とする規定
モデル就業規則とは異なり、副業・兼業を許可制としている例や、一切禁止している例なども見られます。
(副業・兼業)
第○条 労働者は、あらかじめ会社の許可を得た場合に限り、勤務時間外において副業又は兼業をすることができる。
(副業・兼業)
第○条 労働者は、勤務時間の内外を問わず、一切副業又は兼業をしてはならない。
上記の例では、「副業」「兼業」が許可制または禁止の対象とされています。
「副業」「兼業」は抽象的な用語ですが、特段の事情がない限りモデル就業規則の「他の会社等の業務に従事すること」と同義に解釈するのが合理的と考えられます。
上場株式等への投資は、原則として副業に当たらない
会社員として働く人の中にも、株式や投資信託に投資する人が増えてきました。
副業を制限する就業規則の規定は、過度な疲労や情報漏えいなどにより、本業に支障が出ることを防ぐためのものです。
証券取引所に上場されている株式や投資信託などを購入するだけなら、本業への支障は通常生じません。したがって、一般的な上場株式等への投資は、就業規則で定められた「副業」や「兼業」に当たらないと考えられます。
他の会社の役員に就任する場合は、副業に当たる
非上場会社の株式を取得する場合でも、役員などに就任して実際の業務を行うのでなければ、「副業」や「兼業」に当たる可能性は低いと思われます。
これに対して、株式の取得に伴って他の会社の役員に就任し、その会社の経営や業務に参画する場合は、「副業」や「兼業」に該当すると考えられるので注意が必要です。
また、同業他社の役員を兼業する場合は、就業規則における競業避止義務の規定に抵触しないかどうかも確認しましょう。
投資を事業として行う場合は、副業に当たる可能性がある
投資を事業として行う場合は、就業規則で定められた「副業」や「兼業」に当たると判断される可能性があります。
投資が事業に該当するかどうかは、金額の規模やかける時間の長さなどによって判断されます。たとえば以下のような投資は、「副業」や「兼業」に当たる可能性が高いと思われます。
- デイトレーダーとしてほぼ毎日相場に張り付き、頻繁に株式やFXの取引を行う
- 複数の不動産を購入したうえで、長い時間をかけて物件の管理を行う
- 投資によって本業の収入を上回る利益を得ている
- 会社を設立し、法人口座で投資を行っている
(目次へ戻る)
就業規則で副業を禁止・制限することの問題点
就業規則で副業を禁止または制限する例はよく見られますが、副業の禁止・制限が常に認められるわけではありません。
本来であれば、勤務時間外でどのような活動をするのかは従業員の自由です。
勤務時間外の従業員に対して、会社が指揮命令を行うことはできません。したがって、勤務時間外に副業をすることを、会社が過度に制限することもできないはずです。
ただし従業員は、勤務時間中は職務に専念する義務や、勤務先の会社に迷惑をかけない義務を負っています。
勤務時間外における副業でも、上記の義務に違反し得るものについては、就業規則による制限が認められると考えられます。
就業規則に定められた副業の禁止・制限が有効なのかどうか、どの範囲で効力を持つのかなどについては、法的な観点からの検討が必要です。
事業的な規模で投資を行うなど、就業規則の副業規定への抵触が懸念される場合は、必要に応じて弁護士などにご相談ください。
(目次へ戻る)
投資そのものが就業規則で制限されているケースもある
就業規則では、株式などへの投資そのものが制限されているケースもあります。
たとえば証券会社の従業員等については、インサイダー取引を防止する観点から、株式などへの投資が許可制とされている例がよく見られます。
その他の業種の会社でも、取引先の株式を取得してはならないなど、一部の投資が制限されている例が見受けられます。
投資に取り組む際には、就業規則に投資を制限する規定がないかどうかを確認しましょう。また、法律で禁止されたインサイダー取引などを行わないように注意することも大切です。
(目次へ戻る)
勤務時間中に株式市場をチェックすると、就業規則違反のおそれがある
株式投資などを始めると、株式市場の動きが常に気になってしまうという人がたくさんいます。特に日本の株式市場は、会社の勤務時間中に開いているので、スマートフォンで値動きをチェックしたくなるかもしれません。
しかし休憩時間を除き、勤務時間中に頻繁に株式市場をチェックすることは避けるべきです。勤務時間中に私的な用事でスマートフォンを操作していることが発覚すると、就業規則で定められた専念義務違反の責任を問われるおそれがあります。
株式市場をチェックするのは、勤務時間が終了してからにしましょう。
*1 厚生労働省「モデル就業規則 令和5年7月版」p90
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。