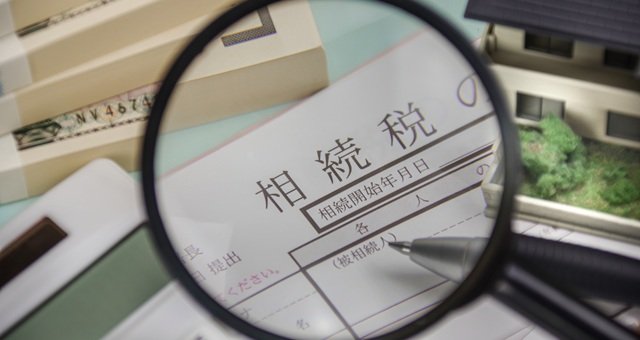亡くなった家族の遺産を相続したときは、相続税などの税金がかかることがあります。本記事では、遺産相続に関する税金の基礎知識を解説します。
家族の遺産を相続すると、税金がかかる?
家族の遺産を相続したときにかかる主な税金は「相続税」です。また、不動産を相続したときには、所有権移転登記の申請に係る費用として「登録免許税」がかかることがあります。
相続税は、必ずかかるわけではありません。後述するように、課税対象となる財産が基礎控除額を超える場合に限って相続税がかかります。
2023年(令和5年)には日本国内で157万6016人が亡くなっていますが、そのうち相続税の申告書が提出されたのは15万5740人です。*1
申告漏れなどを度外視すると、相続税がかかっているのは全体の10%程度であることが分かります。
(目次へ戻る)
遺産にかかる税金(1)|相続税
相続税は、亡くなった人の遺産などを取得した家族に対して課される税金です。
相続税がかかる財産
相続税は、以下に挙げる財産について課されます。遺産に加えて、生前に受けた贈与などにも相続税が課されることがあります。
(a)相続財産
家族が亡くなった時点で所有していた財産(遺産)です。借金などの債務も負っていた場合は、債務の額を差し引きます。
(b)みなし相続財産
相続財産ではないものの、家族が亡くなったことをきっかけに取得する財産です。以下の財産などがみなし相続財産に当たります。
- 生命保険の死亡保険金、損害保険金
- 死亡退職金
- 生命保険の解約返戻金請求権のうち、亡くなった家族以外の人が被保険者であるもの
- 定期金および定期金に関する権利
- 特別縁故者が受けた財産分与、特別寄与料
- 著しく低額の対価による財産の譲渡、債務免除などによって得た利益
- 遺言による信託の受益権
(c)家族が亡くなる前3~7年間に受けた生前贈与
家族が亡くなる直前に生前贈与をして、相続税を不当に減らすことを防ぐため、以下の期間に受けた贈与には相続税が課されます。*2
<2026年12月31日までに亡くなった場合>
亡くなる3年前の日から死亡日まで
<2027年1月1日から2030年12月31日までに亡くなった場合>
2024年1月1日から死亡日まで
<2031年1月1日以降に亡くなった場合>
亡くなる7年前の日から死亡日まで
(d)相続時精算課税制度*3の適用を受けた贈与
相続時精算課税制度とは、生前に受けた贈与に対してまとめて相続税を課す制度です。
亡くなった父母や祖父母などから受けた生前贈与につき、相続時精算課税を選択した場合は、その贈与に対して相続税が課されます。
基礎控除額を超えると相続税がかかる
上記の課税対象財産の総額が基礎控除額を超えると、相続税がかかります。相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算します。*4
※亡くなった人の養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めます。
※相続放棄をした人も、法定相続人の数に含めます。
たとえば、相続人が亡くなった人の妻と子2人の計3人である場合、相続税の基礎控除額は4800万円となります。
この場合、課税対象財産の総額が4800万円を超えると相続税がかかります。
相続税はいくらかかる?
相続税の計算方法はかなり複雑です。実際にかかる税額の計算には専門的な検討を要しますので、税理士のアドバイスを受けましょう。
亡くなった人に配偶者がなく、法定相続人が子のみであるケースについて、相続税の総額の目安を紹介します(説明を簡略化するため、控除や特例の適用はなし)。

*国税庁の基準により筆者作成
上記の表で示したのは、相続税の総額です。各相続人が納める相続税額は、実際に取得した財産の割合に応じて割り振られます。
たとえば課税対象財産の総額が1億円、相続人が子3人(A・B・C)のケースでは、相続税の総額は630万円です。
課税対象財産のうち、Aが2分の1、BとCが4分の1ずつを取得したとすると、A・B・Cが納めるべき相続税額は以下のようになります。
B:157万5000円
C:157万5000円
相続税の申告方法・納める時期
相続税の申告は、亡くなった人の納税地(住所地)を管轄する税務署に対して、申告書等を提出して行います。 *5
申告書等の提出は、税務署の窓口への持参、郵送またはe-Taxによって行うことができます。
相続税の申告期限は、相続の開始(=家族が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内です。相続税の納付も、同期限までに行う必要があります。
(目次へ戻る)
遺産にかかる税金(2)|登録免許税
亡くなった家族が所有していた不動産を相続した場合は、相続登記の手続きを行う際に登録免許税がかかります。
不動産の相続登記を申請する際には、登録免許税がかかる
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)から相続人へ不動産の名義の変更(所有者権の移転登記)を登記簿に記録することをいいます。
相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に、法務局に対して相続登記を申請しなければなりません。*6
登記申請の際には、登記申請書への収入印紙の貼付や電子納付などの方法により、登録免許税を納める必要があります。
なお、不動産の相続後3年以内に登記申請を行う義務は、「相続人申告登記」の申請によって果たすこともできます。*7
相続人申告登記は、通常の相続登記の手続きよりも簡単であり、登録免許税もかかりません。
ただし、相続人申告登記がなされただけでは、相続した不動産を第三者に売却することはできません。不動産の売却に先立ち、正式な相続登記を申請する必要があります。
登録免許税はいくらかかる?
相続によって不動産を取得した場合にかかる登録免許税の金額は、不動産の価額の0.4%です。*8
不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。
固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が不動産の価額を認定します。
(目次へ戻る)
株式や投資信託を相続した場合、税金はかかる?
亡くなった人が保有していた株式や投資信託も、相続の対象になります。金融機関に相続手続きを申請し、手続きが終われば、株式や投資信託を相続人の口座へ移管してもらえます。
株式や投資信託を相続しても、直ちに税金が課されるわけではありません。売却した時点で利益が出た場合に、その時点で所得税(復興特別所得税を含む)と住民税が課されます。
したがって、相続した株式や投資信託は、売却せずに保有し続ける場合には、売却するまで税金がかかりません。
ただし、配当や会社分割などが発生する場合は、それに伴う所得に対して、所得税や住民税が課されることがあります。株式や投資信託の税金について分からないことがあれば、税理士に相談してアドバイスを受けましょう。
*1 出所)国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」p1
*2 出所)国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
*3 出所)国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
*4 出所)国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
*5 出所)国税庁「相続税の申告のしかた(令和6年分用)」
*6 出所)法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
*7 出所)法務省「相続人申告登記について」
*8 出所)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。